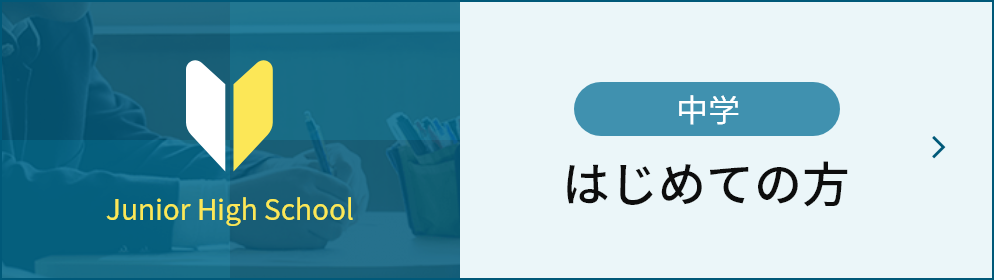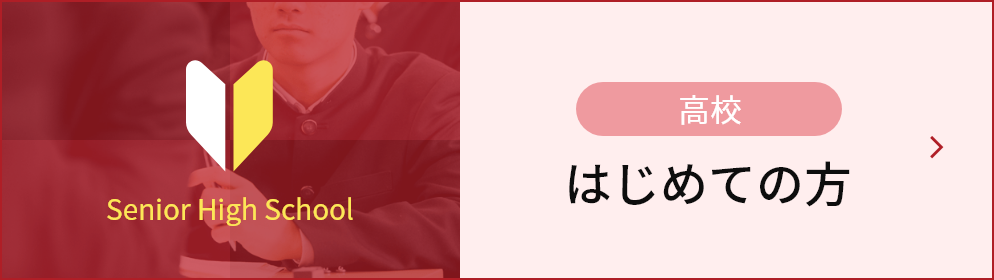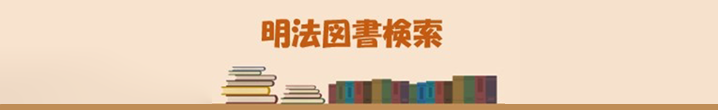中高一貫教育
建学の精神「世界平和に貢献する人材育成」の実現
緑のキャンパス充実の施設で 少人数教育
「教員1人に生徒14人」の少人数で、
一人ひとりの個性を大切にしながら
「教師と生徒の人間的なつながり」を深める教育
東京ドーム1.2倍の広大なキャンパスと充実した施設で
学習も部活動も思いっきりできる!
きめ細やかな 学習サポート
- 「週末課題&週明けテスト」で基礎学力確立(中1~中2)
- 徹底した定期考査の解き直し(中1~中3)
- 「3点固定」で学習習慣を身につける(中1~中3)
- 放課後学習会(テラコヤ)(中1~中3)
- 入試チャレンジ(中3)
- 年間100講座以上の講習会 + チューターもいる『学習道場』で自学自習(中1~高3)
- 一人ひとりに合わせた『駿台サテネット』で学力アップを支援(高1~高3)
- 進路アドバイザーの指導(高1~高3)
- 受験対策の特別講習(高3)
本物にふれる STREAM教育
中1~中3
- 理科専門棟で豊富な理科実験(中3では「サイエンス・ラボ」)
- 全教室に「電子黒板&Wi-Fi環境完備&PC端末」でICT環境も充実
中1~高1
- プロが指導する少人数器楽レッスンと「仲間とつくる」多種多様な美術授業
高1~高3
- 一人1台のPC端末+全教室に電子黒板&Wi-Fi環境完備
実績豊富な グローバル教育
中1~高2
英検対策講習(希望者)
高1・高2
希望者は誰でも海外研修(シアトル)
高1
GSP ターム留学(ニュージーランド)
高2~高3
英語でゼミ授業『21世紀』
21世紀型スキル 4つのC 「4Cプログラム」
中1:プレプログラム
サイエンスGEとGSP foundationの入門を1年間学びます。
サイエンスGE
- プログラミングの「3つの基礎構造」
GSP foundation
- 英語レッスン
- English Shower Campへの参加
中2~中3:メインプログラム①
サイエンスGEかGSP foundationのどちらかを選んで深く学びます。
サイエンスGE
- ロボットプログラミング
- 高度な実験
- ロボットプログラミングの大会に出場(SRC・RCJ)
GSP foundation
- 英語レッスン(英検対策)
- English Shower Camp
- Tokyo Global Gateway
- British hillsへの参加
高1:メインプログラム②:プログラムの集大成
サイエンスGE
中学入学生のみでプログラムを継続、RCJや情報オリンピック出場に挑戦
GSP foundation
週1コマの講座を通じて、ターム留学の準備をし、高1の3学期からターム留学に参加
将来を見据える キャリア教育
- 生徒の実行委員会が企画・運営する体育祭・明法祭などの学校行事(中1~高3)
- プロジェクトアドベンチャーで問題解決力と協働する力をつける(中1~中3)
- 探究旅行(中1)
- 保護者・著名人による進路講演会(中2)
- フィールドワーク(中2)
- 卒業生による進路講演会(中1~中3)
- 研究旅行(中3)
- キャンパスツアーなどの豊富な進路イベント(高1~高2)
- 進路アドバイザーが一人ひとりの進路をサポート(高1~高3)
- 修学旅行(高2)
- 現役合格に向けたロードマップ(高2~高3)
- 大学教授講演会(中3~高1)
- OBOG懇談会(高1~高2)
教科指導
明法の教科指導は本物の中高一貫です。
きめの細かい指導を通じて、
生徒の知的好奇心を育て、
社会に貢献できる人材を育てます
明法の教科指導は基礎を身につける中1・中2から大学受験に向けた実践力をつける高3まで、一貫したプログラムで行われます。熱い心をもった明法の教員が、「本物に触れる教育」とともに、きめの細かい教科指導を通じて、生徒たちの知的好奇心を育て、社会に貢献できる人材づくりを行っています。
国語
国語は全ての教科の土台となるものです。文章を読解する力が不足していれば、他教科の教科書を正確に読むこともできないからです。
では「国語力」とは? 「読む・書く・聞く・話す」力のことです。この四つをバランス良く伸ばしていくことが必要です。
まずは「読む・書く・聞く・話す」の基礎力を養います。易しめの文章を丁寧に読み込むことから始め、文章とはいかなるものかを把握したうえで、少し歯ごたえのある文章に挑戦していき、文章読解のコツをつかんでいくことを「読む」に位置づけます。それを踏まえ、テーマに基づいて自ら考え、それをしっかり表現して文章にあらわす「書く」を進めていきます。さらに、自分で調べたことを発表するスピーチを授業内で積極的に取り入れながら「話す」を鍛え、仲間の発表をまとめたりする「聞く」にも繋げていきます。それらを通じて、国語に関する主体的な学習を行えるようにします。
中3からは古典の授業を発展的に行い、高校で教わる内容に関しても取り扱いながら先人の思考に触れ自分の視野を広げていきます。その一方で、漢字検定は全員が中3終了までに3級以上の取得を目指します。
数学
明法独自の数学科一貫カリキュラム
中学から高校にかけての数学は、小学校の「直感的理解(目で見てさわれる物の数的性質を見出す)」から、「論理的思考(論理を追って正しい結果に到達する)」への移行期間と位置づける事ができます。その移行は、生徒の発達段階に応じて、しかも知的好奇心を充分刺激しながらなされなければなりません。そのため本校では、内容の関連・流れを重視した独自の項目配列によるカリキュラムを組んでいます。基礎・基本は徹底した反復練習によってその定着を図り、その基礎的な事柄が、より興味深く高いレベルで理解されるよう、時には学習指導要領を超えて、問題集・参考書・自主教材などで発展的な事項も学習します。また、効率的なカリキュラムと時間増により、各学年では次の学年の内容を先取りして学習することができ、高校3年生では受験演習に充分な時間をかけることができるようになっています。
明法数学科の習熟度別授業
本校数学科では各学年ごとに、習熟度別クラス編成を取り入れています。創立以来の少人数のクラス編成を、さらに少人数の習熟度別クラスに編成することによって、個々に合ったきめ細かい指導が可能になっています。本校の習熟度別授業は、基礎に重点を置く授業から発展に重点を置く授業まで、クラス毎に授業内容は異なり、生徒の個々の状況にきめ細かく対応します。習熟度別授業は、生徒を差別・選別するものではなく、生徒がより良く理解するために個々の状況に対応する一時的な手段であると本校数学科は考えています。ですから定期考査は同じ問題で行い、途中で編成替えを行います。そして、授業の枠にとどまることなく自主的に学習する生徒の意欲がこのシステムを支えています。
英語
社会、経済の急速なグローバル化の進展、国を超えた人材の流動性の高まりという国際化が一層進む中、英語によるコミュニケーション能力の向上が課題となっています。
英語科では、新学習指導要領や入試改革に対応した「英語4技能」を、本校独自の21世紀型教育(「4つのC」「ICT活用」「答えが1つでない課題」)を通じて、またMeiho Can-do Listに基づいて総合的に育成していきます。
1年次は英語を使った活動をとことん「楽しむ(have fun)」、2年次は教材に対して「知的な興味を持つ(take interest)」、3年次は英語を通して物事に「感動し(be moved)」、物事を「議論する(think and talk)」、といったことを目標としています。授業に加えて、家庭学習用の課題を通して、「短時間でも“毎日”勉強すること」を習慣化していきます。
英語科の教育目標(中高共通)
- 英語学習を通じて世界平和に貢献できる人間として成長する土台を築く
- 外国語(英語)を介して国際社会における諸問題を認識し、それらを解決するための行動力を身に付ける。
- 母語(日本語)を駆使して行う強靭な思考力と、鋭敏で柔軟な感受性を身に付ける。。
- 物事を他者の立場に立って考える術を身に付ける。
- 自己をより情緒的・論理的に表現する術を身に付ける。
中学修了時の到達目標
- 英語の学習方法を知り、英語学習を楽しむ。
- 簡単な情報や考え方を、英語で理解したり表現したりすることができる。
- 英語の基礎基本を身に付けた上で、学力テストや検定試験において学習の成果を出す。
明法英語教育の特徴
- 全学年で習熟度別授業を実施(単位数の少ない科目ではクラス授業もあり)
- クオリティーを重視した英会話授業を提供(中1~高1)。なお、中3、高1では、分割少人数で英会話授業を展開
- 英語で理解し、考え、表現する授業、「21世紀」(高2・高3)の設置《選択科目》
理科
明法の理科授業では「実験の充実」が重視されます。実験自体とその前後の学習活動には、明法理科が目指す「科学する心」を育む様々な要素を見出すことができます。
では、その要素とは何でしょうか。
- 自分の頭で考え、理解したことを前向きに実行することができる。
- 道具器具の性質を理解し、安全適切に使いこなすことができる。
- 座学授業と実験が刺激し合い、自ら探究心を高めることができる。
これらは実験に臨む心得であり、明法で身に着けさせたい基本的な資質そのものなのです。そしてこれらが、「学力向上」にとどまらず、自然現象に共鳴しながら「豊かに生きる力」を育むと考えます。「科学する心」は言葉や説明だけで実感できるものではありません。基本をみすえた実践の繰り返しが肝要なのです。
明法では、他校に類を見ない「理科棟」に豊富な実験観察機器を(こだわりの顕微鏡も)揃えており、これまでも一貫して少人数で、一人ひとりが実験・観察を十分体験できる授業を展開しています。さらに、中3の授業では、このような通常の授業4単位に加え、「実験のみの授業(実験ラボ)」を1単位分行っています。この実験授業では、中学理科を実験の力でしっかりまとめ、学習の自立をはかり、より濃密な高校授業を受け入れ消化する準備を整えます。
このように明法理科では、実験を軸に展開するひとつひとつの活動に、知識習得以上の価値も加味し、本物の理科教育を提供しています。
社会
社会科は、世の中を理解し、自分がどのような形で社会に貢献できるかを考える科目です。中高一貫の効率的なカリキュラムで、資質・能力の3つの柱(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力など」「学びに向かう力・人間性など」)をバランス良く育てます。具体的な方法として「社会科300選」を実践しています。社会を理解するための基礎的な用語や人名・出来事などを、「社会科300選」という形にまとめ、反復練習による知識の定着をはかります。
学習で得た知識を使いこなすために、「社会科新聞」を中学の各学年で作成します。自分が伝えたいことは何なのか、伝えるために必要な情報を自分で集め、まとめることを通じて、社会に出て必要とされる「表現力」の基礎を育てます。
授業においては、一方的な「教える」「教わる」だけの形ではなく、少人数制を生かし、生徒との対話を重視した双方向の授業で問題をより深く考察していきます。また、ICT機器や視聴覚教材を積極的に活用し、より知識を吸収しやすく工夫した授業を展開します。地理の授業で周辺地域を実際に歩いて特徴を調べたり、外国人留学生を招いて意見交換会を開くなど、生徒自身による「体験」も重視しています。
美術
明法の美術では『「想像」と「創造」を習慣づける』ことをテーマとし、【自ら作り出す喜び】を体感することを大切にしています。様々な出会い、他者との関わり、考え方の共有の中でこそ、新しい発見をすることができます。その発見が「想像を超えるきっかけ」となり、独創的な造形をつくり出すことへとつながります。他者の意見や自分の存在を大切にする心を養うことを通して、自分の思い描くことが、少しずつ実現して、自分の想像以上の「創造」になっていくことの素晴らしさを学んでいきます。
授業内容[中学3年間で以下の中から9つ程度を実施)]
色と形の基本、抽象画モビール、モダンテクニック、化学反応による石こう作品、デザインの学習、陶芸、版画、染色、手作り絵の具制作、パッチワーク、彫刻、現代アート作品 など
※個人制作とアクティラーニング形式のグループ制作、外部講師(クリエイター、デザイナー、アーティスト)による授業、学外の方との交流の中で制作する内容も含まれています。
美術教育の重点テーマ
共感と協同的対話形式の制作
他者と協同で創作活動を行う。様々な経験と価値観の拡大により、物事を「見る力」、他者の考えや思いを「想像する力」を養い、制作の中で「感動を共有する喜び」を体験する。
「児戯的魅力」による発展的自己表現
表現欲求は発達段階の中で、今までの経験値による技術力や価値観から消極的になってくる。そこで「面白いが、これが果たして美術なのか」と思わせる題材を準備する。本能的な欲求を想起させること、楽しいと素直に思えることを実行する力を持ち続けさせたい。
学校(生徒)と地域をつなぐ創作活動
造形活動を通して、コミュニケーション能力や美的に限らない判断力を育み、文化やコミュニティの伝承発展の大切さを学ぶ。また、世代を超えたつながりに親しみ、創作活動を軸とした自己実現や社会参加の機会とする。
音楽
音楽
オーケストラ授業に必要な読譜能力を身につけ、初歩の音楽理論を理解させます。また、クラス合唱により音楽の本質が私たちの持つ「声」であることを学びます。名作の時代背景や作曲家の人物像に触れ、作品をより深く学ぶことにより、生涯学習へと導きます。
B&W社のメインスピーカーとBOSE社のサブスピーカーシステムにより擬似的に音楽室にコンサートホールや教会の響きを再現して、圧倒的な高音質オーディオ装置で音楽を鑑賞します。また、150インチの大スクリーンでオペラ・音楽映画・ミュージカル等の鑑賞をします。
オーケストラ
オーケストラ授業は専用の校舎「音楽棟」で行われ、特殊楽器などフルオーケストラを余裕で編成できる楽器数を備えています。
授業は5名の各楽器のエキスパートによるグループレッスンの形で行われ、全員が初心者であるため、楽器の持ち方、指使い、音の出し方から丁寧に始めます。やがてグループのアンサンブル(合奏)が始まり、中2の文化祭(9月下旬)には学年全体オーケストラの演奏が可能になります。更に中3では本格的なオーケストラ曲に挑戦します。
集大成は満員の観客の前での演奏です。学年が一つとなる一体感、美しいハーモニーを作り出す喜び、また大きなステージを終えた達成感は生徒達の生涯の宝物になります。
過去の演奏曲
ファランドール(ビゼー)マイスタージンガー前奏曲(ワーグナー)美しく碧きドナウ(Jシュトラウス)スラブ行進曲(チャイコフスキー)交響曲第5番ハ短調(ベートーヴェン)歌劇カルメンより(ビゼー)等
保健体育
明法中学校で行う体育の授業では、体育嫌い運動嫌いな生徒が、体育好き運動好きな生徒となり、全校生徒みんなが楽しめる体育の授業を展開します。サッカーの授業では、FIFA公認の広さがある第1グラウンドと人工芝の第2グラウンドを使用します。日本の伝統と文化を学ぶ柔道の授業では、スプリングが設置されている専用の柔道場で安全に授業を行います。その他、バレーボール、バスケットボール、ソフトボールなどの球技、短距離走、長距離走などの陸上競技、マット運動、鉄棒などの器械運動などなど数多くの種目を広大で充実した体育施設で行います。また、保健の授業では、中学1年生~3年生まで成長段階に応じて授業を展開し、思春期の心身の状態、社会問題とされる体力低下や不規則な生活、感染症などについて理解を深めていきます。そして、これらの他にも体育祭、マラソン大会、スポーツ大会、部活動、各種の保健体育的活動を通して学んだ知識を生かし、日頃から健康的な生活を営み、積極的にスポーツに親しめる生徒に育ってほしいと願っています。
技術家庭
技術分野 「物作り」を通して学ぶ
現在または、将来生活に必要な技術を「物作り(演習や作業)」を通じて学習し生活に役立てることを目的とし授業を進めています。材料と加工に関する技術では、製図を基礎から学び自由設計で各自作品制作に取り組み工夫や想像力を身につけます。また作品制作にとどまらず材料と環境の関わりについても学習を深めていきます。学習エネルギー変換に関する技術では、身のまわりの電気エネルギー利用(発電の仕組みや家電製品の仕組み等)や動力の利用、そして身のまわりの家電製品に使用されている電子部品を学習し電気工作を行います。情報に関する技術では、コンピュータの基礎知識(ハードウェア・ソフトウェア等)となる事柄やフローチャートを用いたコンピュータ制御学習(問題解決能力等)の演習、さらに、Googleコラボラトリーでプログラミング演習を行います。また、中学生として情報社会における必要な知識(著作権やモラル、多様なメディア特性等)も学習していきます。
家庭分野 「実習」を通じて学ぶ
生活に身近なことを取り上げ、興味をもって取り組める授業を行います。よりよい生活をしていくために、また自立と共生を目指して、生活に必要な知識や技術を習得し、これからの生活における課題を解決する方法を学びます。生活するためには、知識だけでなく、実際に手や体を動かして体験することが必要です。そのために実習を行い、その過程で生活を工夫し、創造する能力や物を作る技術を習得します。調理実習では、計量や野菜の切り方、出汁のとり方などを学び、1人で簡単な食事が作れるようになることを目指します。 被服実習では、基礎縫いや刺繍を使ってコースターやファイルカバーなど様々な作品を製作し、自分の衣服の手入れを行うことが出来る技術を身につけます。他にも、安全で心地よい住まいについて学び、自分が住みやすいと思う間取りを考えたり、消費者としてより適切な購入の仕方を学び、環境に配慮した消費生活を工夫できるような知識を主体的に学習していきます。